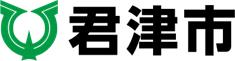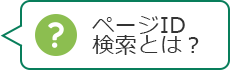本文
国保の給付
療養の給付
病気やケガをしたとき、国民健康保険を取り扱う医療機関で治療が受けられます。
医療機関で支払う医療費の負担割合は次のとおりです。
| 区分 | 負担割合 | |
|---|---|---|
| 小学校入学前(未就学児) | 2割 | |
| 小学校入学後から70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上 | 2割または3割 | |
※1 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方(現役並み所得者)は3割負担となります。
ただし、下記の(1)から(4)までのいずれかに該当する場合は、2割負担となります。
(1)70歳以上の国保被保険者が1人で、国保被保険者の収入金額が383万円未満。
(2)70歳以上の国保被保険者が2人以上で、国保被保険者の収入金額の合計が520万円未満。
(3)70歳以上の国保被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額の合計が520万円未満。
(4)70歳以上の国保被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額)の合計額が、210万円以下。
※2 医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる高額療養費が適用される場合があります。詳しくは高額療養費のページをご覧ください。
療養費
次のような場合で医療費を全額支払ったとき、保険の対象となる額のうち、自己負担分を除いた額を支給します。
- やむを得ずマイナ保険証、資格確認書または保険証を持たずに医療機関で治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたはり、灸、あんま、マッサージを受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセット、ギブスなどの補装具代
- 輸血のための生血代
- 海外渡航中に病気やケガなどで医療機関を受診したとき(ただし、治療目的の渡航は除く)
出産育児一時金
国保に加入している方が出産した場合(妊娠12週以上の死産、流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。
平成26年12月31日までの出産
- 産科医療補償制度対象の方 42万円
- それ以外の方 39万円
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの出産
- 産科医療補償制度対象の方 42万円
- それ以外の方 40.4万円
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産
- 産科医療補償制度対象の方 42万円
- それ以外の方 40.8万円
令和5年4月1日以降の出産
- 産科医療補償制度対象の方 50万円
- それ以外の方 48.8万円
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した脳性麻痺児に対する補償制度で、妊産婦の皆さまが安心して出産できるよう分娩機関が加入する制度です。産科医療補償制度に関する詳しい情報は(財)日本医療機能評価機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※会社の健康保険に1年以上被保険者として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、以前加入していた健康保険に出産育児一時金の支給を申請することもできます。
| 手続方法 | |
|---|---|
| 直接支払 | 出産したときに支給される出産育児一時金を限度に出産費用に充てることで、あらかじめまとまった現金を用意した上で出産費用を支払うという経済的負担の軽減を図る制度です。 この制度を利用するためには、世帯主が医療機関等との間で出産育児一 時金の支給申請と受取に係る代理契約を締結する必要があります。 また、出産費用が出産育児一時金に満たない場合には差額を支給しますので、国保年金課へお問い合わせください。 |
| 受取代理 | 世帯主が出産育児一時金の受取を医療機関等に委任することにより、医療機関等に出産育児一時金が支払われます。直接支払制度と同じく出産時の経済的負担が軽減されます。利用するには市への申請が必要です。 |
| 償還払 | 直接支払、受取代理を使用しないときは、出産した医療機関等に出産費用を支払ったのち、国保年金課へ申請することで、出産育児一時金等が支給されます。 |
葬祭費
国保に加入している方が死亡したときは、葬儀を行った方に対し葬祭費として5万円を支給します。
第三者行為
交通事故など第三者の過失によって傷病を受け、国保を使って治療を受ける場合、届け出が必要になります。第三者の過失による傷病にかかる医療費は原則として加害者が費用を負担するべきもので、国保は一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。