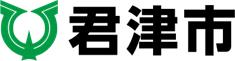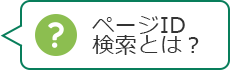本文
後期高齢者医療制度の給付のご案内
お医者さんにかかるときは必ず忘れずにマイナ保険証か資格確認書のいずれかを提示してください。
医療費の自己負担の割合(一部負担金の割合)は、マイナポータルや資格確認書等で確認できます。(1割、2割および3割)。
所得区分
| 自己負担 の割合 |
所得区分 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 3割 |
現役並み 所得者3 |
住民税課税所得(課税標準額)(※ア)が690万円以上の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者 |
|
現役並み 所得者2(※イ) |
住民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者 | |
|
現役並み 所得者1(※ウ) |
住民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者 | |
|
2割 |
一般2 | 住民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者及び同じ世帯にいる被保険者
|
|
1割 (※エ) |
一般1 | 住民税課税世帯で、同一世帯に現役並み所得者、一般2に該当する被保険者がいない方 |
| 区分2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(区分1以外の被保険者) | |
| 区分1 |
|
※ア 住民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
※イ、ウ 現役並み所得者1または現役並み所得者2の方は、基準収入額適用申請ができる場合がありますので、下の「基準収入額適用により自己負担の割合が3割から2割(1割)になる方の条件」をご確認ください。
※エ 平成27年1月以降の判定に適用
基準収入額適用により自己負担の割合が3割から2割になる方の条件
| 世帯内の 被保険者数 |
収入の基準 |
|---|---|
| 1人 | 本人の収入が383万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上のとき |
| 収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70から74歳までの方がいる場合は、その方と被保険者本人の収入合計額が520万円未満、かつ本人の「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上のとき | |
| 2人以上 | 被保険者の方の収入合計額が520万円未満かつ被保険者の「年金収入+その他の合計所得」が320万円以上のとき |
基準収入額適用により自己負担の割合が3割から1割になる方の条件
| 世帯内の 被保険者数 |
収入の基準 |
|---|---|
| 1人 | 収入が383万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得」が200万円未満のとき |
| 収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70から74歳までの方がいる場合は、その方と被保険者本人の収入合計額が520万円未満かつ本人の「年金収入+その他の合計所得」が200万円未満のとき | |
| 2人以上 | 被保険者の方の収入合計額が520万円未満かつ被保険者の「年金収入+その他の合計所得」が320万円未満のとき |
入院したときの食事代
入院したときの食事代は1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
区分1・2の方は、入院の際に「マイナ保険証」、または「限度区分の記載のある資格確認書」が必要になります。資格確認書に限度区分を記載するためには国保年金課窓口または各市民センター窓口で申請してください。
| 自己負担 の割合 |
所得区分 | 1食あたりの食費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 |
510円※ |
|||
| 2割・1割 | 一般 | ||||
| 1割 | |||||
| 区分2 | 90日までの入院 | 240円 | |||
|
区分2 (長期該当) |
過去12か月の間で「区分2」であった期間の 入院日数が90日を超える入院 |
190円 | |||
| 区分1 | 110円 | ||||
※ただし、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円。
令和7年4月より、食事療養標準負担額が見直されました。
療養病床に入院する場合
| 自己負担 の割合 |
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者 | 510円※ | 370円 | ||||||
| 2割・1割 | 一般 | ||||||||
| 1割 | |||||||||
| 区分2 | 240円 | ||||||||
| 区分1 | 140円 | ||||||||
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | |||||||
※一部医療機関では470円
医療区分2・3の方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や指定難病の方など入院の必要性が継続する方)や、回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、食費として、上の【表1】と同額を負担します。居住費は1日当たり370円(指定難病の方は0円)となります。
高額療養費
1か月(同じ月内)の保険適用分医療費が高額になり下の【表3】の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、超えた分が高額療養費として支給されます。支給対象の方には申請書がご自宅に郵送されます。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
|
現役並み 所得者3 |
252,600円
|
|
|
現役並み 所得者2 |
167,400円
|
|
|
現役並み 所得者1 |
80,100円
|
|
| 一般2 |
6,000円+(医療費−30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方を適用 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
57,600円
|
| 一般1 |
18,000円 (8月から翌年7月の年間限度額144,000円) |
|
| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
医療機関の窓口支払いをあらかじめ自己負担限度額までにするには
所得区分が「現役並み所得者2」、「現役並み所得者1」の方は、医療機関に「マイナ保険証」「限度区分の記載のある資格確認書」のいずれかを提示すると、窓口ごとの支払いが上の【表3】の額までに抑えられます。
医療機関へ所得区分のわかるものを掲示しないと所得区分「現役並み所得者3」の額になりますが、申請により、高額療養費としてあとから支給を受けることができます。
所得区分が「区分1」、「区分2」の方は、医療機関に、「マイナ保険証」「限度区分の記載のある資格確認書」のいずれかを提示すると、窓口ごとの支払いが上の【表3】の額までに抑えられます。
医療機関へ所得区分のわかるものを掲示しないと所得区分「一般1」の額になりますが、申請により、高額療養費としてあとから支給を受けることができます(入院時の食事代を除く)。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証の新規交付終了について
令和6年12月2日以降、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の新規交付は行いません。
医療機関へ所得区分の掲示が必要な場合は、「マイナ保険証」または「限度区分の記載のある資格確認書」を使用してください。資格確認書に限度区分を記載するためには国保年金課窓口または各市民センター窓口で申請が必要です。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合に、限度額を超えた分が各保険者から支給される、高額医療・高額介護合算制度があります(500円以下の場合は支給されません)。
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 |
|---|---|
|
現役並み 所得者3 |
2,120,000円 |
|
現役並み 所得者2 |
1,410,000円 |
|
現役並み 所得者1 |
670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 区分2 | 310,000円 |
| 区分1 | 190,000円 |
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合の限度額(月額)は10,000円です。この場合「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、国保年金課窓口または各市民センター窓口で申請してください。
また希望がある場合、申請をすれば資格確認書へ特定疾病の区分、発行期日の記載をすることができます。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症
療養費(あとから費用が支給される場合)
次のような場合で、診療に要した費用の全額を支払ったときは、国保年金課窓口または各市民センターで申請して認められると、自己負担額分を除いた額が療養費として払い戻されます。
- やむを得ない理由で、マイナ保険証や資格確認書なしで受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関で受診したとき
- 医師が治療上必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めて、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき
- 医師が必要と認めて、保存血ではなく、生血を輸血に用いて、血液提供者へ生血代を支払ったとき
(注)血液提供者が親族の場合は対象外 - 海外に渡航中、治療を受けたとき
(注)治療が目的で渡航した場合は対象外
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときに、申請により葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
その他の給付
訪問看護療養費(訪問看護ステーションなどを利用したとき)
居宅で療養している方に、医師が在宅診療を受ける必要があると認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、訪問看護に要した費用の1割、2割、または3割のみのお支払で診療が受けられます。
移送費(緊急時などやむをえない場合)
負傷、疾病等により移動が困難な被保険者が、医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむをえず別の病院に移送されたときなど、国保年金課窓口または各市民センター窓口で申請し、広域連合が内容を審査のうえ認めた場合、「移送費」として支給されます。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、その治療に必要な医療費は、相手が支払う損害賠償金の中で負担するのが原則です。
一時的に保険診療を受ける場合は、保険者へ被害の状況等を届け出ることとなっています。
この場合、広域連合で医療費を一時立て替え、後で第三者などへ請求します。
第三者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、お早めに必ず国保年金課窓口で届出をしてください。
(注)自分の過失や業務上でケガをした場合もご相談ください。
届出に必要な書類など
- 第三者の行為による傷病届一式
- 印章(ハンコ)
- 交通事故証明書(後日でも可。警察から交付を受けてください。)
詳しくは下記を参照してください。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>