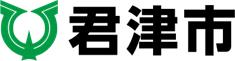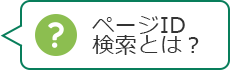本文
後期高齢者医療制度のご案内
後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の方々に「生活を支える医療」を提供するとともに、これまで長年、社会に貢献してこられた方々の医療費を国民みんなで支える「長寿を国民みんなが喜ぶことができるしくみ」です。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する高齢者の医療制度です。
後期高齢者医療制度のしくみ
都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町村と協力して運営しています。
- 千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
後期高齢者医療制度に関するお問い合わせはこちら
- 名 称 千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
- 電話番号 0570−066−046
- 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
広域連合
運営主体(保険者)となり、「保険料の決定」・「医療を受けたときの給付」・「資格確認書の発行」・「資格情報のお知らせの発行」などを行います。
市区町村
「保険料の徴収」・「申請や届け出の受け付け」・「資格確認書・資格情報のお知らせの引き渡し」などの窓口業務を行います。
対象となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人で、申請により広域連合から認定を受けた人
※一定の障がいとは
- 身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級(音声、言語、下肢1・3・4号)をお持ちの方
- 療育手帳(重度)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
上記のどちらかにあてはまるすべての人が対象となります。対象者はそれまで医療を受けていた国保・健康保険組合・共済組合・船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。
対象となる日
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。
資格確認書
- 資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
- 令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず受診できるよう、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
また、全ての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を令和7年7月中に郵送いたします。このとき、マイナ保険証をお持ちの方へも資格確認書が交付されるため、資格情報のお知らせは交付されません。 - 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあれば届け出ましょう。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- なくしたり破れたりしたときは、国保年金課または市民センターで再交付の申請ができます。
紙の保険証の新規交付の終了について
従来の紙の被保険者証は、令和6年12月2日以降、交付(紛失による再交付等を含む)されなくなります。
経過措置として、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、券面に記載の有効期限までお使いいただけます。
※券面の記載事項に変更が生じた方には、資格確認書が交付されます。
詳細につきましては、下記リンクから、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
・紙の保険証の新規交付終了について<外部リンク>
・資格確認書について<外部リンク>
・「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について<外部リンク>
・保険証について<外部リンク>
保険料は大切な財源です
後期高齢者医療制度の医療に係る費用のうち、みなさんが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市町村)が約5割を負担、現役世代からの支援金(若年者の保険料)で約4割を負担し、残りの1割を高齢者の皆さんに納めていただいた保険料で負担しています。みなさんの保険料は医療費のほかに健康診査の費用や葬祭費などの財源になります。