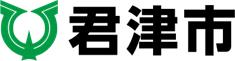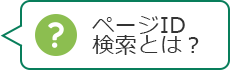本文
野良猫の問題が増えています
飼い主のいない猫
飼い猫には、犬のような登録制度がなく、また、屋内飼育や迷子札の装着が徹底されていないため、屋外飼育の飼い猫と、飼い主のいない猫との判別がつきません。このような猫による、庭やゴミ荒らし、糞尿などの迷惑問題が発生しています。
飼い主のいない猫をお世話するときは
餌を与えるだけの管理では、繁殖などによって、厳しい環境で生活しなければならない猫が増加し、結果、周辺での迷惑問題も大きくなっています。動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こさないように、注意しましょう。
1 避妊・去勢手術を実施し、これ以上増えないようにしましょう。
2 できるだけ自分の敷地内で餌を与え、後片付けをしましょう。
3 トイレ等を設置し、糞の後始末をしましょう。
周辺住民の地域環境の悪化とならないよう理解を得ながら、十分な配慮をし、不幸な猫を増やさないだけではなく、トラブルを防ぐためにも、猫とのつきあい方を考えてみましょう。
知っていますか?地域猫活動
地域猫活動とは、地域住民が主体となって、地域に住む飼い主のいない猫(野良猫)に避妊・去勢手術を行うことで繁殖を制限し、餌やトイレの管理を協力して行い、飼い主のいない猫と地域住民との共生を目指す取り組みです。
活動の手順
1 情報収集
猫の数、性別、餌場、飼い猫との判別、被害状況等について情報収集し、確認しましょう。
2 地域住民との相互理解
地域猫活動の実施には、地域住民の理解が必要です。
3 活動のルール作り
参加者で、役割分担等を決め、無理なく活動が継続できる体制を作ります。
4 避妊・去勢手術
不幸な子猫の増加を防ぐとともに、発情期の鳴き声等の問題を防ぐために、避妊・去勢手術を実施します。
5 その後の管理
地域猫活動を始める前に
地域猫活動には猫の捕獲や避妊・去勢手術や周辺住民へのお知らせ、餌やりや糞の清掃など多くの活動があり、費用や時間がかかります。1人でやりきるのは困難なため、周囲で活動に協力してくれる人を探しましょう。
また、猫が苦手で地域猫活動に賛同してくれない人もいる可能性があります。地域猫活動は猫のためだけではなく野良猫によるトラブルを減らすことを目的とした活動であることを知ってもらいましょう。